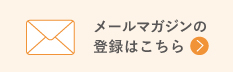冬こそビタミンDの摂取が大切な理由|不足する原因と摂取する方法
SUMMARY
- ・ビタミンDの働きや冬に摂取することが大切な理由
- ・冬にビタミンD不足を招く理由
- ・冬にビタミンDを摂取する効率的な方法
- ・ビタミンDを摂って、冬でも元気な体を維持しよう
ビタミンDは、体の調子を整えるのに必要な栄養素です。特に冬はビタミンDが不足しがちなので、積極的に摂る必要があります。しかし、ビタミンDは具体的にどんな働きがあるのか、1日にどのくらい摂取すべきか、詳しく知らない人は多いのではないでしょうか?
そこで、今回はビタミンDの働きや、摂取目安について詳しく解説します。さらに、冬に積極的に摂りたい理由についても紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。
ビタミンDの働きや冬に摂取することが大切な理由
ここからはビタミンDの働きについて、詳しく解説します。
● ビタミンDの働き
ビタミンDは、主にカルシウムの働きに影響を与える栄養素です。日頃から適切な量を摂取することで、健康維持に役立ちます。生活習慣対策や食習慣が気になる人は、積極的に取り入れるといいでしょう。
● 冬の季節にビタミンDの積極的な摂取が大切な理由
冬は体調を崩しやすい時期です。冬は暖房をたく機会が多く、屋外と室内の気温差が大きい傾向にあります。気温差が大きいと、体のコンディションが崩れて体調を崩しやすくなります。
そこでおすすめなのがビタミンDです。ビタミンDには、体の調子を整える作用があるため、意識的に毎日の食事から摂るといいでしょう。
● 1日に摂取するビタミンDの目安
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、ビタミンDの摂取量目安は18歳以上の場合、男女ともに1日あたり8.5μgです。しかし、ビタミンDの摂取量目安は年齢によって大きな差があります。
日本骨粗鬆症学会の「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年度版」によると、高齢者のビタミンD摂取目安量は、1日あたり10〜20µgです。日光に当たる機会が少ない高齢者は多く、ビタミンDの生成が比較的少ないと考えられているため、他の年代よりも多く設定されています。
なお、成人や高齢者ともに、ビタミンDの耐容上限量は1日あたり100µgです。サプリメントを飲む際は、ビタミンDの耐容上限量に注意しましょう。
【出典】 「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf
【出典】 「ビタミンD」 (厚生労働省)
https://www.ejim.ncgg.go.jp/public/overseas/c03/10.html
冬にビタミンD不足を招く理由
冬にビタミンD不足が起こりやすい原因には、日光が関係しています。ビタミンDは日光を浴びることでも生成されます。多くのビタミンは、食事からでしか摂取できないため、非常に珍しい特徴といえるでしょう。ここからは、ビタミンDと日光の関係について詳しく解説します。
● 日照時間の減少
冬は日照時間が短いため、紫外線に当たる機会が少ない傾向にあります。ビタミンDの生成をするなら、冬は積極的に日光浴をする必要があるでしょう。ビタミンDを生成するために必要な日光浴の時間は、15~30分が目安とされています。
また、地域や時間帯、季節によって推奨される日光曝露量には差があります。北海道など北部の場合はより長く日光に当たる必要がありますが、沖縄など南部の場合は短時間でも、十分な量のビタミンDを生成できます。
以下の記事では、ビタミンDの生成に必要な日光曝露量について詳しく解説しています。
ビタミンDの生成のため日光を浴びた方が良い?日光浴の目安の時間
● 防寒対策による皮膚の露出減少
紫外線には「中波長紫外線(UV-B)」と「長波長紫外線(UV-A)」の2種類があります。ビタミンDの生成に関わるのは、前者のUV-Bです。
UV-Bは衣服を通さないため、肌の露出面積が少ないと、ビタミンDの生成を妨げてしまいます。冬は厚着をする機会が増えるため、ビタミンDが不足しやすくなるのです。
● 外出する機会の減少
冬は気温が低いため、外出を控え、室内で過ごす時間が長くなりがちです。また、地域によっては路面状況が悪いため、外に出られない場合もあるでしょう。
UV-Bは衣類のほか、ガラスを通過することもできません。ビタミンDの生成を促すためには、直接肌に紫外線を当てる必要があるため、外出する機会が減ると、ビタミンDが不足しやすくなるでしょう。
冬にビタミンDを摂取する効率的な方法
ここからは、ビタミンDを効率よく摂取する方法について紹介します。できるものから取り入れ、ビタミンD不足の解消を目指しましょう。
● 日中に散歩や日光浴をする機会を増やす
冬でも適度に日光を浴びるには、日中など気温が高い時間帯に外出するといいでしょう。早朝や夕方以降は紫外線量が少ないため、効率よくビタミンDを生成するなら日中がおすすめです。
また、日中のほうが気温が高いため、過度な防寒対策が不要な場合もあるでしょう。無理のない範囲で、皮膚の露出面積を増やし、ビタミンDの生成を促しましょう。
なお、紫外線はシミやシワの原因とされていることから、日光浴を避ける人が多い傾向にあります。紫外線によるエイジングが気になる場合は、腕や脚だけ日光に当てるようにするといいでしょう。
● 食事で積極的に取り入れる
ビタミンDを多く含む食品には、以下のようなものがあります。
・かつおの塩辛
・あんこう
・キクラゲ
・しいたけ
・鮭
魚やキノコ類は、ビタミンDを多く含みます。ただし、これらを日常的に食べている人は多くないため、意識的に摂取する必要があるでしょう。なお、ビタミンDを効率よく摂取するために、食品を天日干しにしたり、油で調理したりするのも有効です。
しいたけは、生よりも乾燥したもののほうが、ビタミンDの量が多い傾向にあります。しいたけを食べるときは、天日干しにするのがおすすめです。
また、ビタミンDは脂溶性のビタミンのため、油と一緒に食べると吸収効率がアップします。そのため、炒める、揚げるなどの調理法が有効です。
ビタミンDが多い食品ランキング|1日の摂取量の目安
【出典】「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html
● サプリメントを活用する
普段の食事や、日光浴では足りない場合、サプリメントでビタミンDを補うのも一つの手です。サプリメントの中には、1粒で1日に必要なビタミンDを摂取できるものもあります。
なお、サプリメントを利用する際は、安全性や使い方に注意が必要です。サプリメントは薬ではないため、病気の治癒を期待して使用するものではありません。病気が疑われる場合は、病院を受診するようにしましょう。
また、薬と併用する場合は、医師や薬剤師に相談しましょう。サプリメントの成分によっては、薬の副作用が強まったり、効果が弱くなったりすることがあります。
【出典】 「健康食品の正しい利用法」 (厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/kenkou_shokuhin00.pdf
ビタミンDを摂って、冬でも元気な体を維持しよう
この記事では、ビタミンDを冬に積極的に摂るべき理由を中心に解説しました。日照時間が短いことや、外出する機会が減少することが原因で、冬はビタミンDが不足しやすくなります。
ビタミンDは、毎日の健康を支える重要な栄養素です。外出をしたり、ビタミンDが豊富な食品を取り入れたりして、ビタミンD不足の解消を目指しましょう。
また、ビタミンD不足が気になる場合は、サプリメントを利用するのも1つの手です。「Lypo-C Vitamin C+D」なら、1包でビタミンCを1000mg、ビタミンDを2,000IU(50μg)摂取できます。ぜひ、毎日の健康維持に役立ててください。
記事監修
長谷川悠院長
You’s clinic Aoyama
順天堂大学医学部・同大学大学院卒業後、順天堂医院形成外科・同医院放射線科に所属。
都内の美容クリニックにて勤務した後、複数のクリニックにて院長に就任。
2021年3月にYou's clinic Aoyamaを開院。
プライベート空間で患者さまに寄り添いながら、日々美容・健康と向き合っている。