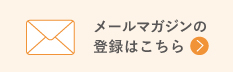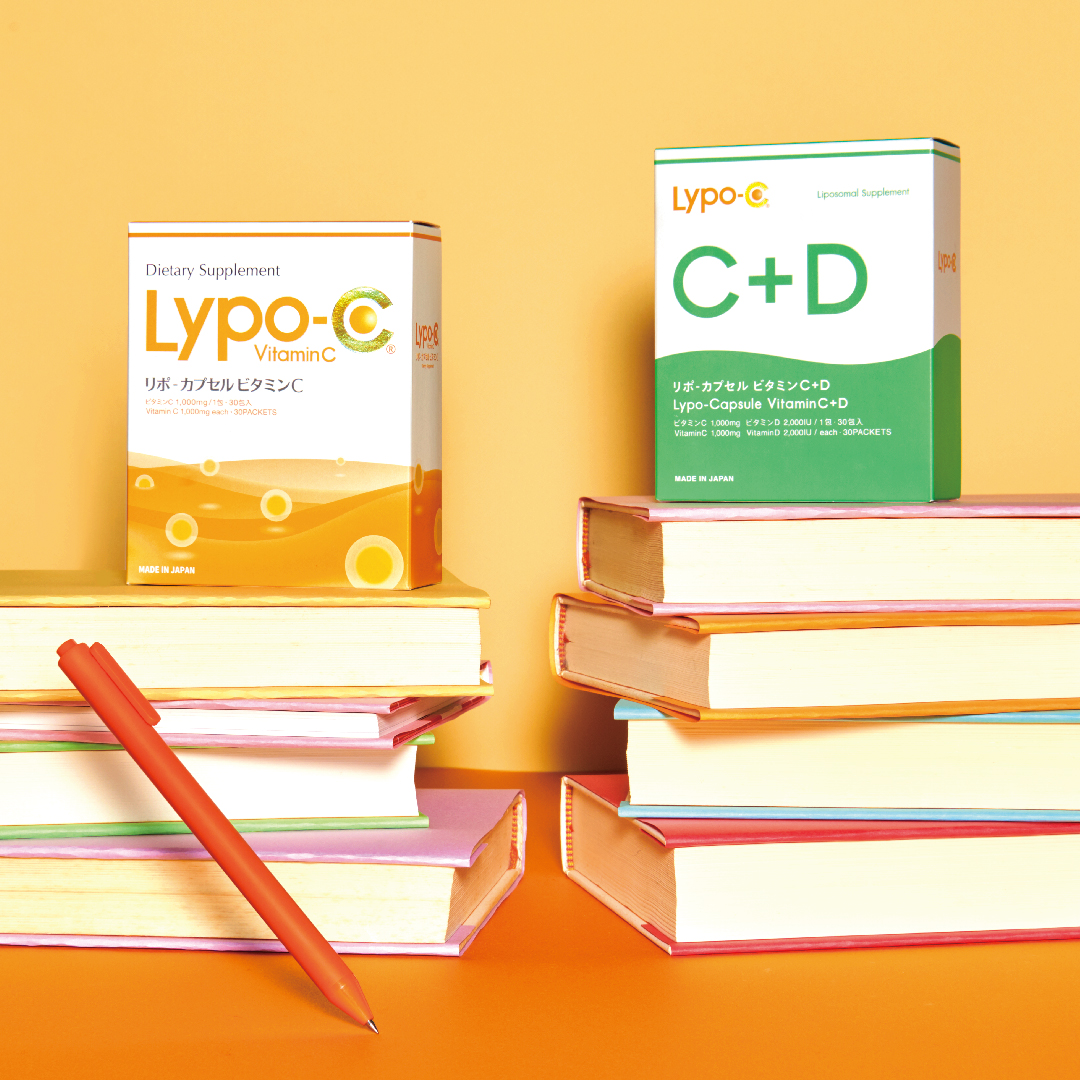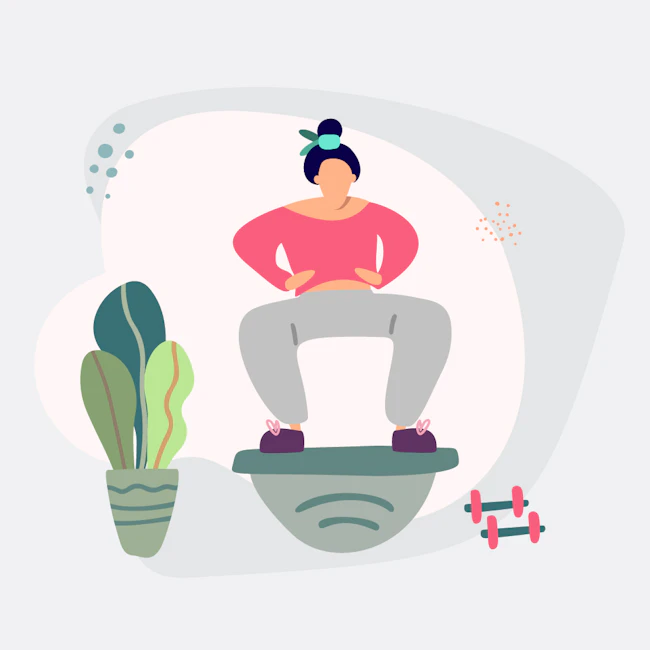
筋トレ効果を高めるために摂りたい栄養素と摂取する方法
SUMMARY
- ・筋トレ時に摂りたい栄養素は?
- ・筋トレ効果を上げるための栄養素の摂り方
- ・筋トレの効果をより上げる方法
- ・バランスの取れた栄養で筋トレ効果を上げよう
普段から筋トレに励んでいる方の中には、摂取する栄養について、関心がある方も多いのではないでしょうか?食事は身体を作る重要な要素なので、理想の自分に近づくためにも、しっかりチェックしておきたいものです。また、効率良く筋力をアップさせるためには、栄養の摂り方にポイントがあります。
この記事では、筋トレ時に摂りたい栄養素やおすすめの摂取方法について紹介します。筋トレの効果を上げたい方は、ぜひチェックしてください。
筋トレ時に摂りたい栄養素は?
トレーニングの成果を十分に上げるには、さまざまな栄養をバランス良く摂ることが重要です。ここからは筋トレの効果を上げるために重要な栄養を紹介します。
●タンパク質
タンパク質は炭水化物、脂質とともに「三大栄養素」と呼ばれている栄養の1つです。筋肉や臓器の細胞を作るもとになります。
タンパク質は20種類の「アミノ酸」が結合してできた化合物です。20種類のアミノ酸のうち、9種類は体内で作ることができない必須アミノ酸で、かならず食事から摂取する必要があります。
また、タンパク質には、肉や魚、卵などの「動物性タンパク質」と、穀物や豆類などの「植物性タンパク質」の2種類があります。
動物性タンパク質は吸収率が97%と、ほとんどが体内に吸収される性質があります。一方、植物性タンパク質は吸収率が84%です。
動物性と比較すると、植物性タンパク質は吸収率が悪いものの、植物性タンパク質が含まれる食品は低脂質で、食物繊維が豊富です。タンパク質は、動物性と植物性の2つをバランス良く摂ることが大切です。
【動物性食品】
食材名 (可食部100g当たりのタンパク質量)
にわとり 若どり ささみ 生 /(23.9g)
しろさけ 新巻き 生 /(22.8g)
鶏卵 卵黄 生 /(16.5g)
【植物性食品】
食材名 (可食部100g当たりのタンパク質量)
油揚げ 生 (23.4g)
木綿豆腐 (7.0g)
豆乳 (3.6g)
●炭水化物
炭水化物も「三大栄養素」の1つです。ダイエットのために、炭水化物を避ける方もいますが、活動に必要なエネルギーを、脳や骨格筋に供給する重要な役割を担っています。
炭水化物にはトレーニングの効果を増大させたり、パフォーマンスを向上させたりするプラスの作用が期待できます。
炭水化物が不足すると、十分な力を発揮できない、判断力が低下する、といったことも起こりえるため、適量摂取することが大切です。
また炭水化物は、吸収されてエネルギー源になる「糖質」と、吸収されずエネルギーにならない「食物繊維」に分けられます。
食物繊維には、胃腸の調子を整えたり、脂質や糖分、塩分を体外に排出したりするはたらきがあります。日本人は食物繊維が不足しやすい傾向にあるため、意識的に摂取するといいでしょう。
食材名 (可食部100g当たりの炭水化物量)
はちみつ (81.9g)
食パン (44.2g)
ごはん(精白米、うるち米) 炊飯 (34.6g)
マカロニ・スパゲッティ ゆで (28.5g)
中華めん ゆで (25.2g)
じゃがいも (15.9g)
●脂質
脂質は三大栄養素の一つで、人体のエネルギー源となる栄養です。エネルギーの生成に加え、脂溶性ビタミンの吸収を助ける役割があります。
脂質の摂りすぎは、肥満の原因になることが広く知られていますが、不足すると身体の不調に繋がることがあります。具体的には、体力低下やホルモンバランスの乱れ、皮膚トラブルなどです。
また、脂質は主に「脂肪酸」から構成されており、常温で固形化する「飽和脂肪酸」と常温で液状化する「不飽和脂肪酸」の2種類があります。
「飽和脂肪酸」は肉や乳製品に、「不飽和脂肪酸」は魚やオリーブオイルに多く含まれます。飽和脂肪酸は摂りすぎると生活習慣病の原因となるため、1日のカロリーの7%以下にすることが推奨されます。
食材名 (可食部100g当たりの脂肪酸総量)
オリーブ油 (74.04g)
無発酵バター 食塩不使用 (73.00g)
もも 脂身 (56.08g)
アボカド (18.7g)
いわし類の缶詰 油漬け (11.45g)
ヒレ 赤身 (3.13g)
●ビタミン
ビタミンは、生活習慣対策や健康に役立つ栄養です。ビタミンには「水溶性ビタミン」と「脂溶性ビタミン」の2つに分類することができます。
水溶性ビタミンは、血液などの体液に溶け込み、余分なものは尿として排出されます。一方、脂溶性ビタミンは、脂肪組織や肝臓に貯蔵される栄養です。
どちらも体内で生成されることはほとんどないため、食事から摂取する必要があります。
このように、ビタミンにはさまざまな種類がありますが、特に筋トレ時に摂取したい栄養としてビタミンB群やビタミンDが挙げられます。
ビタミンB群は、水溶性のビタミンで糖質やたんぱく質、脂質の代謝に関わる成分です。ビタミンDは、脂溶性ビタミンで健康な身体を維持する働きがあります。
食材名 栄養 (可食部100g当たりの含有量)
かつお ビタミンB6 (0.85g)
まぐろ 赤身 ビタミンB6 (0.76g)
豚もも ビタミンB1 (0.96g)
ブロッコリー ビタミンB1 (0.17mg)
しろ鮭 焼き ビタミンD (31.2μg)
さんま 焼き ビタミンD (13μg)
●ミネラル
ミネラルとは、生体を構成する主な4元素「酸素」「炭素」「水素」「窒素」以外のものの総称です。厚生労働省が策定する「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、以下の16種類を人の身体に必要な「必須ミネラル」としています。
・ナトリウム
・塩素
・カリウム
・カルシウム
・マグネシウム
・リン
・硫黄
・鉄
・亜鉛
・銅
・マンガン
・コバルト
・クロム
・ヨウ素
・モリブデン
・セレン
筋トレで大量の汗をかくと、ミネラルが失われます。特に筋トレ時は、カリウムやカルシウム、マグネシウムを意識的に摂るといいでしょう。こむら返りを防ぐ効果を期待できます。
食材名 栄養 (可食部100g当たりの含有量)
刻み昆布 カリウム (8,200mg)
ドライマンゴー カリウム (1,100mg)
プロセスチーズ カルシウム (630mg)
牛乳 カルシウム (110mg)
ごま マグネシウム (370mg)
焼きのり マグネシウム (300mg)
【参考】
「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf
【出典】
「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/amenu/syokuhinseibun/mext00001.html
筋トレ効果を上げるための栄養素の摂り方
同じ栄養を摂るなら、筋トレの効果が出やすい食事をしたいですよね。ここからは、筋トレ効果を上げるための栄養素の摂り方を紹介します。
●栄養バランスの良い食事を摂る
筋トレ中の食事、というとタンパク質をイメージする方もいますが、バランス良く栄養を摂ることが大切です。タンパク質に加え、脂質や炭水化物、ビタミン、ミネラルを積極的に摂るようにしましょう。
筋トレに必要な栄養素も含んだ嬉しいレシピ!
●間食のおやつや栄養補助食品を活用する
3食の食事のみで栄養を摂り切ることが難しい場合は、間食やサプリメントを併用するといいでしょう。特にバナナやさつまいもはミネラルが豊富なので、間食におすすめです。
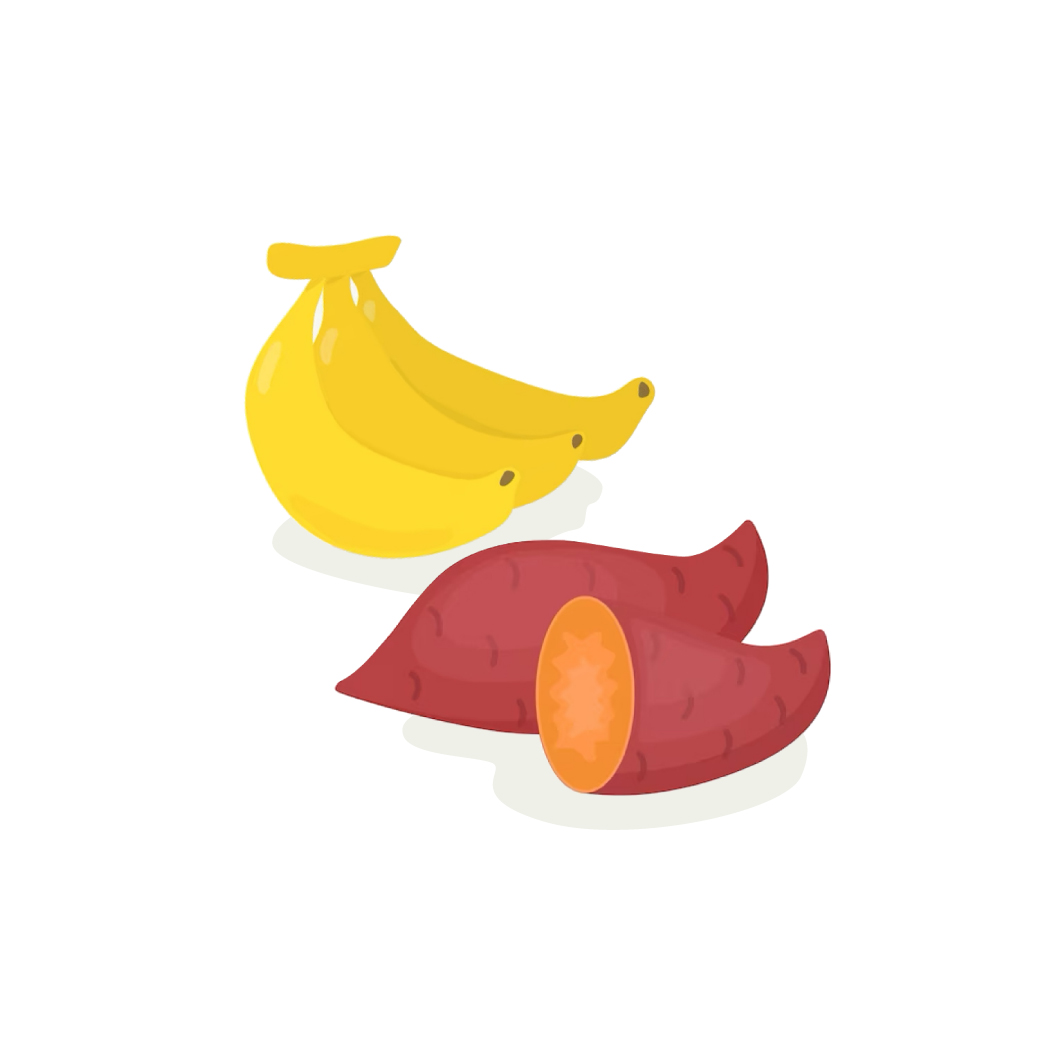
また、スナックバーやプロテインなど、栄養バランスが考慮された食品もあります。ドラッグストアで気軽に買うことができ、バリエーションも豊富なので、ぜひ活用してみましょう。
筋トレの効果をより上げる方法
筋トレの効果を上げるには、食事を摂るタイミングにもポイントがあります。ここからは、筋トレの効果をより上げる食事方法について解説します。
●運動前に食事をする
トレーニングをするタイミングは、空腹でも満腹でもない、食後2~3時間後がおすすめです。空腹は体の栄養素が足りない状態です。エネルギー不足によって筋肉が分解され、基礎代謝が下がる恐れがあります。
また、満腹時の筋トレもおすすめできません。食後の筋トレは、消化活動を阻害してしまうため、消化不良や吐き気が起こることもあります。
●筋トレ後45分~1時間内にタンパク質を摂る
筋トレ後の45分~1時間は、筋肉の回復能力が高まる時間帯です。この時間にタンパク質を炭水化物と一緒に摂ると、筋力アップがしやすくなります。肉や魚などの食事が理想ですが、難しい場合はプロテインや豆乳などでタンパク質を摂取するといいでしょう。
バランスの取れた栄養で筋トレ効果を上げよう
この記事では、筋トレ時に摂りたい栄養素やおすすめの摂取方法について紹介しました。筋トレ時は、タンパク質以外にもビタミン類や炭水化物を摂取することが大切です。
また、毎日の健康維持には、ビタミンCも重要です。Lypo-Cなら、1包で1,000mgのビタミンCを摂取できます。身体のコンディションを整えたい方や、美容の調子が気になる方はぜひチェックしてください。
記事監修
水谷皮フ科クリニック院長
水谷治子先生
水谷皮フ科クリニック
東京医科大学卒業。東京医科大学病院皮膚科、都内美容皮膚科クリニックなどを経て2012年、水谷皮フ科クリニック開院。
一般皮膚科、小児皮膚科に加え、しみ、たるみなどの美容皮膚科を診療している。