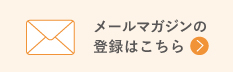日本に学ぶ癒やしと綺麗の智慧 ~美を紡ぐ人々〜 Vol.3 新潟県・南魚沼市 今成漬物店 今成要子さんが大切にする、許容の精神とは
SUMMARY
- ・雪国ならではの智慧から生まれた心身に沁みる発酵食
- ・南魚沼に戻り気づいた、自分も他人も労わる心身の健全さ
- ・若い世代にも、伝統の発酵文化を知ってもらいたい
新潟県・南魚沼市 今成要子さん
今成漬物店 4代目
いまなりようこ●1971年新潟県・南魚沼市生まれ。高校まで地元で暮らし東京へ。青山学院女子短期大学へ進学し、卒業後は、株式会社思潮社、シャネル株式会社(現シャネル合同株式会社)、ウェブデザインなどの会社で働く。40歳で地元に戻り、家業である今成漬物店の仕事を始める。伝統の山家漬づくり、新商品の開発を通して、南魚沼の発酵食の素晴らしさを広めている。何があっても“まっ、いいか”の精神で乗り切ることが信条。趣味は読書。11歳の子をもつ母でもある。
世界中のホテル&スパ、各地に息づく健康や美のルーツ、文化を取材し続けている、トラベル&スパジャーナリストの板倉由未子さんが執筆するコーナー。
今年は、日本各地で、その土地を愛しながら身も心も健やかに生き、美を紡いでいるさまざまな職業の方にフォーカスを当て、その土地から学んだ知恵や明日を前向きに生きるヒントを紐解いていきます。
それぞれの方のお話から、その土地にも興味をもち、日本を一緒に旅してみませんか?
今回は、板倉さんが“山家漬は口に入れるたびに、日本人であることの幸せを感じる”と語る、新潟県・南魚沼市にある「今成漬物店」の4代目、今成要子さんへのインタビューです。
雪国ならではの智慧から生まれた心身に沁みる発酵食

板倉
以前、銘酒『八海山』を製造する「八海醸造」を取材させていただく機会があり、この地域で“おっかさま”と呼ばれ親しまれた故・南雲仁会長が、今成さんの「山家漬(やまがづけ)」に八海山の酒粕が使われていることを、非常に誇らしくて語られていました。その時から、いつかお伺いしてみたいと思っていました。
今成さん(以下敬称略)
ありがとうございます。山家漬は、南魚沼産の山菜、そして越瓜、錦糸瓜、なす、きゅうりという地野菜を八海山の酒粕に漬け込んだ粕漬けです。
八海醸造さんには、貴重な純米大吟醸酒の酒粕を納めていただき、こちらこそ感謝をしております。酒粕なしに山家漬をつくることはできませんから
板倉
口に入れた途端、ふわっと日本酒のよい香りがして、野菜の甘みと歯ざわりが心地よい。炊き立てのご飯があったら、他に何もいらないなぁと思い、幸せな気持ちになります。いつごろからつくられているのでしょう。
今成
今成家(鴻池屋)は、江戸時代からさまざまな事業を行っておりまして、粕漬づくりも300年以上の歴史があります。山家漬が誕生したきっかけは、100年ほど前、曽祖父の隼一郎が牧場と野菜づくりを始め、親友の歌人で書家の會津八一先生に粕漬を贈らせていただいたところ非常に喜ばれ、西行の『山家集』にちなんで山家漬と命名してくださったのです。それ以来、本格的に漬物業を始めるようになりました。
板倉
築200年の蔵に木桶が並べられ、その中で山家漬は静かに発酵、熟成しているのを拝見し、歴史と浪漫を感じました。漬け込みはどのように行われているのでしょう。
今成
山家漬は、塩、酒粕、野菜というこの土地の素材と発酵菌の作用で、添加物は一切加えずにつくられます。作業は野菜の旬と収穫に合わせ、4〜6月に山菜、6〜8月にきゅうりや越瓜、7月の2日間だけ錦糸瓜、なすは8〜9月に、契約農家さんが厳選した素材を届けてくれます。
生漬け(塩漬け)、酒粕を入れて中漬け、さらに酒粕を加えて本漬けし、1〜2年の月日をかけて、昔ながらの製法でつくっています。野菜そのものを味わうより、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの栄養価が高いのです。雪国ならではの健康を維持する智慧ですね。
板倉
手間と時間をかけて、あの豊かな味わいが生まれる。そして、冬は漬け込み作業は行わない。待つことがおいしさを育む要因なのですね。
今成
はい。ここは雪深い土地ですし、人間が自然のリズムに合わせて生きていく必要があります。今日出かけよう思っていても雪で出られないことも多いので、人々は物事をある程度の範囲内であれば許容し、長いスパンで考えます。山家漬も、同じ木桶の中でも上部と下部、桶ごと、年によって味が微妙に違うのです。おいしいという範囲内に幅があることを、お客様も理解し楽しんでくださっているのです。
板倉
その時その時の南魚沼の土地の恵みを味わい、まったく同じ味には2度と出合えない。ナチュラルワインの楽しみ方にも似ていますね。ひとつひとつ味が違うことが個性であり、巡り合う喜びがあると思います。
南魚沼に戻り気づいた、自分も他人も労わる心身の健全さ
板倉
幼い頃から、歴史ある家業を継がれようと思われていたのですか。
今成
いえ、まったく考えていませんでした(笑)。“ここには目新しいことがない”と思い、東京で進学して就職もしました。出版社、海外高級ブランドなどに勤め、20年以上東京で暮らしていたのですが、心から情熱を注げることがない虚しさを感じていました。そんな時、パートナーとの間に子どもができ、子育てをするなら南魚沼の方がよいと思い、別居婚という形でこちらに戻ってきたのです。結局、パートナーとは同居をすることがないまま別れてしまいました(笑)。ですから、戻ってきて初めて、本格的に家業を手伝うようになったのです。
板倉
そうでしたか。お子さんの誕生によって、南魚沼へ導かれたようですね。家業に携われるうちに、徐々に後継者となる心構えができていったのでしょうか。
今成
時を経ながら、少しずつですね。弟もいるのですが、私が戻ってきた時にはすでに結婚し、この地を離れていました。最初はただ手伝っていましたが、日々、お客様から“これこそ人間が食べるものです”、“人生最期の食事にしたい”など、ありがたいお言葉をいただくのです。
驚きの連続でしたが、人々からそのようにいっていただけるものに関われることは幸せだと思うようになりました。また、最近では発酵食への関心も高まり、国内外の名シェフからも注目していただき、“これこそ日本の宝だから、頑張ってください”などと応援していただいています。
板倉
そうですね。物や情報があふれていますが、山家漬のようなシンプルなものにはなかなか出合えない気がします。そして、2021年に病気をされたことも転機になられたとか。
今成
そうなのです。それまでは東京にいた頃も含め動けるだけ働いていたので、無理が重なったのでしょう。うちのお客様でもある担当医のかたが“一病息災、ひとつくらい体調で気になることや病気があった方が、自分を労わるようになり、健康でいられますよ”とおっしゃったのです。
以来、自分や周りの人に対しても、以前より心身ともに気を配るようになり、何かが起きても“まっいいか”と思えるようになりました。家業を継ぐことへのプレッシャーからも少しずつ解放され、“気負わずに取り組み、新たな挑戦もしてみよう”と思えるようになったのです。
若い世代にも、伝統の発酵文化を知ってもらいたい

板倉
徐々に土地に根づいていかれるうちに、山家漬の魅力を若い世代の人に伝えたい思いから、100年ぶりの新製品となる「クリームチーズの粕漬」や「つけもなか」を開発されたそうですね。
今成
はい。市役所からお誘いいただき、2021年度の『にっぽんの宝物グランプリ』に参加することを決意しました。予想もしていなかったのですが、「つけもなか」が新潟南魚沼大会<調理・加工部門>、JAPAN大会<スイーツ部門>でグランプリを受賞。部門全国チャンピオンで争われたグランドグランプリでも、最高賞までいただくことになったのです。
板倉
素晴らしいですね!アイデアはどのように生まれたのでしょう。
今成
山家漬の本漬けを経た酒粕は、ものすごく旨味があるのです。以前から捨ててしまうのはもったいないので、何かに使いたいと思っていました。
そこで試しに、クリームチーズを1〜2カ月漬けて熟成させたらおいしくて、周りにも好評だったのです。いろいろと試しましたが、北海道のクリームチーズがいちばん相性がよく、金沢で人口着色料を使わずにきれいに発色するもなかの皮を製造してくれるところを見つけ、その中に挟んでみました。
板倉
見た目も可愛いですし、濃厚な味わいでありながら無添加でヘルシー。お茶にもお酒にも合いますね。甘いものが苦手な方でも気に入ると思います。新製品の製造もあるので、最近、新たな蔵も造られましたが、今後取り組んでみたいことはありますか。
今成
これまでどおり、心を込めて山家漬をつくり続けていきたいと思います。私どもには長くお付き合いをしてくださっているお客様が全国にいて、まるで親戚のように温かく応援してくださっています。
1年に1回はお店に来てくださるかたも多いのです。ありがたいことです。新たな取り組みとしては、若い世代のかたともっと交流し、伝統を大切にしながらも、新たな視点や発想をもっと取り入れていきたいです。ご興味のある方は、ぜひご一報ください(笑)。
板倉
最後に南魚沼の魅力を満喫できる、今成さんがおすすめしたい場所を教えてください。
今成
心を落ち着けたい時は、曹洞宗の禅寺「雲洞庵」へ行きます。お庭がとてもきれいで澄んだ気が漂っています。境内に涅槃図があるのですが、それを眺めていると、人間は大きな宇宙の一部なのだと感じます。
伝統文化を守ろう、保存しようと必死になるのではなく、ひとりひとりがよい人生を歩むことで、素晴らしいものが自然に生まれるのではないかと思えます。
また、家族や気の置けない人とリフレッシュしたい時は「魚沼の里」へ行きます。自然の美しさを感じられる施設で、食事も楽しめます。特に「YUKIMURO WAGYU UCHIYAMA」は、自然を眺めながら、にいがた和牛や雪ひかりポークを味わえます。山家漬と同じ八海山の純米大吟醸酒の酒粕で漬け込んだサラミも最高ですよ!
板倉
雲洞庵は、佇んでいるだけで浄化されますよね。そして、魚沼の里へも久しぶりに行きたくなりました。
さまざまなことが瞬時に展開され手に入る時代ですが、今成さんのお話や南魚沼の風土から、時間をかけること、待つことの重要性を感じました。読者のみなさんも、心身ともに余裕がなく落ち着かないと感じたら、南魚沼を訪れてみてはいかがでしょう。
大らかかつ底力を感じる人々に触れ、元気をいただけると思います。今成さん、今日はありがとうございました。 
今成漬物店
多くの文人たちをも唸らせてきた南魚沼が誇る発酵食・山家漬
南魚沼市六日町で、100年以上愛され続ける「今成漬物店」。看板商品は、南魚沼の山菜や野菜を、銘酒『八海山』の純米大吟醸酒の酒粕で漬け込んだ甘口の粕漬「山家漬」です。
その名づけ親となった歌人・會津八一を始め、多くの文人、俳人、歌人との交流もあり、正岡子規、北原白秋、坂口安吾、海音寺潮五郎などからも、その深く上品な味わいは絶賛されていました。
要子さんの考案で誕生した「クリームチーズの粕漬」や「つけもなか」も大好評で、新規のファンも増えています。
https://kounoikeya-imanari.co.jp/
アクセス:上越新幹線越後湯沢駅から在来線に乗り、JR六日町駅まで約20分。JR六日町駅からは徒歩で約8分。
トラベル&スパジャーナリスト
板倉由未子
Yumiko Itakura
『25ans』などの編集者を経て現職に。世界を巡り、土地に息づく癒やし、健康、食、文化をテーマに、各メディアで五感に訴える旅企画を提案&執筆。政府の国際機関や観光局、企業主催のセミナーなどでも、スピーカーを務める。また、イタリア愛好家としても知られ、『イタリアマンマのレシピ』(世界文化社刊)を構成&執筆。また、日本政府観光局のグローバルキャンペーンでは、リラクゼーション分野の専門家として、日本の癒やしについて語っている。Expert Insights Go Deep Into Japan
photos & realization: Yumiko Itakura