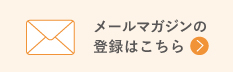紫外線による皮膚や健康への影響は?太陽光から体を守る方法
SUMMARY
- ・紫外線には種類がある?季節によって変わる紫外線量
- ・紫外線が体や肌に与える影響
- ・紫外線から身を守る方法
- ・紫外線の影響を理解し、健康的な毎日を
「肌のためにも紫外線は浴びないほうがいい」といわれていますが、具体的にどのような影響があるのか、詳しく知らない人は多いのではないでしょうか?紫外線は過度に浴びるとマイナスの影響をもたらしますが、適度な日光浴は健康維持のために重要です。
この記事では、紫外線を浴びると、体にどのような変化が起きるのかを紹介します。また、紫外線から体を守る方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。
紫外線には種類がある?季節によって変わる紫外線量
ひとくちに「紫外線」といっても、複数の種類があります。ここでは紫外線の種類とそれぞれの影響について解説します。
● 紫外線の分類は3種類
• UV-A
• UV-B
• UV-C
紫外線には上記の3種類があります。UV-Cは、地球を覆う「オゾン層」によって阻害されるため、地上には届きません。地上に到達するのは、UV-AとUV-Bの2種類です。
UV-Aは、肌の深くにある「真皮層」まで届く波長です。UV-Aは、肌のハリや弾力を維持する成分にダメージを与え、シワやたるみを引き起こす原因となります。UV-Aが降り注ぐ量は、UV-Bの20倍とされています。
UV-Aによる肌の変化はゆっくり起こるため、UV-Bと比較すると分かりにくいです。「気づいたら肌のエイジングが進んでいた」とならないように、日々の対策が必要でしょう。
一方、UV-Bは肌の浅い層に作用する紫外線です。UV-Bは肌表面に炎症を起こし、赤みやほてりを引き起こします。また、黒い色素を作る「メラノサイト」を刺激し、シミやそばかすの原因になることもあります。
地上に到達する紫外線のうち、約10%がUV-Bです。UV-Bは、量が少ないものの、皮膚細胞の遺伝子組織を損傷させ、皮膚ガンを引き起こすこともあります。

【参考】
「紫外線 環境保健マニュアル 2020」(環境庁)
https://www.env.go.jp/content/900410651.pdf
● 紫外線の影響を受けやすい季節と時間帯は?
UV-Aが強くなるのは5~8月、UV-Bが強くなるのは6~9月です。紫外線というと、夏のイメージがありますが、紫外線は1年中降り注いでいます。1月でも夏に比べて、UV-Bは5分の1、UV-Aは2分の1も降り注いでいるので、日焼け対策は必須でしょう。
また、紫外線量は時間帯によっても異なります。夏の場合、約70%の紫外線が午前10時~午後2時に降り注ぎます。そのため、紫外線を避けるのであれば、朝や夕方に外出するといいでしょう。
【参考】
「紫外線についての基礎知識」(日本化粧品工業会 JCiA)
https://www.jcia.org/user/public/uv/knowledge
紫外線が体や肌に与える影響
紫外線を浴びると肌へ負担がかかりますが、まったく浴びないのも問題です。紫外線は、体に重要な栄養素「ビタミンD」の生成を促します。適度に紫外線を浴びることで、健康な毎日を過ごせます。
● 紫外線を浴びてすぐに体や肌に起きる影響
長時間紫外線を浴びると、肌に赤みが出ます。日焼けによって引き起こされる赤みは「サンバーン(紅斑)」と呼ばれる現象です。
細胞がダメージを受けて、皮膚の血流が増加することで起こります。サンバーンは紫外線を受けてから数時間後に出始め、8~24時間後にピークを迎えます。その後2~3日経つと消失するのが通常です。
また、日焼けによって肌が黒くなるのが「サンタン」です。メラニン色素が作られるのは、有害な紫外線を吸収したり散乱させたりして、肌をダメージから守るためと考えられています。サンタンは、紫外線を浴びてから数日後に現れ、数週間~数ヶ月で消失するのが通常です。
なお、紫外線を浴びすぎると、以下の症状が起こることがあります。
水ぶくれ
炎症によって拡張した血管から水分が染み出し、表皮の薄い膜の下にたまって膨れる。
免疫力の低下
体内に生じた異常な細胞や細菌、ウイルスなどを排除しようとする機能が低下する。
角膜炎
角膜の細胞に傷がつくことで、異物感や充血、激しい痛みが生じることがある。
【出典】「紫外線環境保健マニュアル2020」(環境庁)
https://www.env.go.jp/content/900410650.pdf
● 紫外線を長期的に浴びることで体や肌に起きる影響
長年に亘り紫外線を浴び続けると、肌がダメージを受け、シミやシワ、たるみを生じさせます。
さらに、紫外線を浴びることで、良性の腫瘍(脂漏性角化症)と悪性の腫瘍(皮膚ガン)ができることがあります。脂漏性角化症は「老人性いぼ」と呼ばれることもある症状で、少し盛り上がったほくろのようなものができるのが特徴です。
皮膚ガンには「メラノーマ」「基底細胞がん」「有棘細胞がん」など、さまざまな種類があります。基本的に目に見える箇所にできるため、すぐに発見することが可能です。早期に治療することで完治するケースもあるため、気になる場合は早めにクリニックを受診しましょう。
また、長期間紫外線を浴びることは、目にも影響を与えます。以下は、紫外線を浴び続けることで引き起こされる症状の例です。
白内障
水晶体が濁ることで、見えにくくなる病気。紫外線のダメージにより、水晶体の細胞内にあるタンパク質が酸化することで引き起こされる。
翼状片
白目の組織が黒目側に伸びてくる病気。慢性的な刺激が原因と考えられている。
【出典】「紫外線環境保健マニュアル2020」(環境庁)
https://www.env.go.jp/content/900410650.pdf
紫外線から身を守る方法
ここからは、紫外線から身を守る方法を紹介します。美肌を維持したい人は、複数の方法を実施するといいでしょう。
● 太陽に素肌をさらさない
物理的に肌をカバーし、紫外線に当てないようにしましょう。織目や編目が詰った生地を着ると、より効果的です。ただし、夏場は通気性のいい素材を選ぶことが大切です。風を通さない服を着ると、体の熱が逃げず熱中症になるリスクが高まります。
さらに、紫外線をカットする効果のある日傘や帽子も活用すると、より効果が高まります。「紫外線○%カット」と表示された製品もあるので、その数字を目安に商品を選ぶのもおすすめです。
● サングラスをかける
紫外線をカットできる眼鏡を適切に使用すると、眼へのばく露を90%抑えることができます。
サングラスを選ぶ際は、自分のサイズに合ったものを選びましょう。紫外線は上からだけでなく、下や後方からの光も反射して、目に影響を及ぼします。そのため、ある程度の大きさがあり、顔にフィットする製品を選ぶことが大切です。
● 日中は日焼け止めを使用する
紫外線は年中降り注いでいるため、日焼け止めは毎日塗るようにしましょう。また、日焼け止めは用途に合わせて、適切なものを選ぶことが大切です。
日焼け止めの機能を表す単位に「SPF」と「PA」があります。SPFはUV-Bを防ぐ指標、PAはUV-Aを防ぐ指標です。数値が大きく、+の個数が多いほど紫外線の防止効果が高まります。
登山や海水浴など、長時間外で活動するときは、SPFが30以上でPAが+++以上のものを選びましょう。通勤や散歩であれば、それ以下の機能の商品でも、日焼け防止の効果を期待できます。
また、最近では耐水性の高い日焼け止めも登場しました。耐水性は星の数で表され「★(星が1つ)」「★★(星が2つ)」の2種類があります。海水浴や屋外プールなど水に浸かる場合は、UV耐水性が★★の商品を選びましょう。
なお、日焼け止めを使用すると、ビタミンDがほとんど生成されないといったデメリットもあります。ビタミンD不足が気になる場合は、顔だけに日焼け止めを塗り、手や足は日に当てるといいでしょう。

【出典】「紫外線環境保健マニュアル2020」(環境庁)
https://www.env.go.jp/content/900410650.pdf
紫外線の影響を理解し、健康的な毎日を
この記事では、紫外線がもたらす体への影響を詳しく解説しました。紫外線を過度に浴びると、赤みや色素沈着を引き起こします。長期的に浴びることで、シミやシワなどのエイジングを引き起こすため注意が必要でしょう。
しかし、紫外線を浴びると、体に必要なビタミンDの生成が促されます。ビタミンDはイキイキとした毎日を送るのに重要な栄養素です。そのため、過度な紫外線対策は避け、適度に日光を浴びることが重要でしょう。
記事監修

Original Beauty Clinic GINZA院長
佐藤 玲史先生
Original Beauty Clinic GINZA
慶応義塾大学商学部/東京医科歯科大学医学部医学科卒業。
首都圏のクリニック院長などを経て、Original Beauty Clinic GINZAを開業。
皆様から信頼される「美容のかかりつけ医」になるべく日々診療に励んでいる。